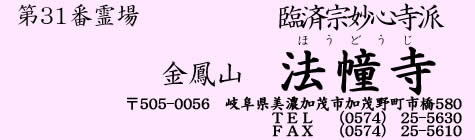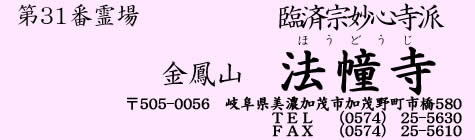当寺は、古くはおよそ7百年程の歴史を持っているみたいですが、定かではありません。今から約470年程前永禄2年(1559)市橋氏の祖、法蔵院殿一乗宗圓大禅定門(位牌有)と言う方が当寺の開基として由緒書きに示されてあり、現在の地名として市橋になっております。
由緒には、戦国時代織田信長公が美濃を攻略する為、蜂屋庄(現 美濃加茂市蜂屋)堂洞城主 岸勘解油政公攻略の折、市橋氏信長公に参じてその功績が認められ、その労を称し戦死者の菩提を弔う為、一宇の堂の建立を許され、その後加治田村龍福寺陽南和尚という方の弟子で祖珊主座と言う方が来往し、本尊聖観世音菩薩を安置し、当初は金剛山法蔵寺と名乗ってましたが、今からおよそ360年程前慶安2年(1649)信州木曽須原郷定勝寺道外和尚の嗣法で石門和尚入寺により寺名を、金鳳山法幢寺と改め当山の開山和尚となりました。
その後寛文2年(1662)加茂郡板倉長蔵寺?嶺和尚(八百津大仙寺愚堂東寔禅師の嗣法)の元に参じて直末となり、当山の創建開山和尚です。
又、天和2年(1682)越前東光寺(伊自良東光寺瑞雲大和尚が開山)6世蘭渓和尚入寺、当山の中興開山和尚です。
幾多の苦難を乗り越え今に到っておりますが、明治20年に入寺住職した鷲見義忠和尚より代々一字に義を付けることが慣例になっております。